Blog記事一覧 > 症状の考え方 | 淀川区・十三で評判の荻野接骨院の記事一覧
こんにちは。
お正月と言う特別な時期から、
日常へとリズムは整ってきましたでしょうか?
今日は細胞の中にいて、
エネルギーを作り出してくれている、
ミトコンドリアについてです。
最近になって、
「ミトコンドリアが大事」という話をよく耳にします。
確かに、
ミトコンドリアは、
エネルギーを生み出すとても重要な存在です。
疲れやすさや、
回復力の低下を語るときに、
避けて通れないテーマやと思います。
ただ、
少しだけ立ち止まって
見ておきたいことがあります。
身体を発電所と配線に例えてみます。
ミトコンドリアは
発電所の役割。
でも、
発電所がどれだけ元気でも、
配線が絡まっていたり
途中で漏電していたり
スイッチが入りっぱなしやったりすると、
電気は
うまく必要な場所まで届きません。
実際の身体でも同じことが起きています。
眠りが浅い
呼吸が詰まっている
常に緊張している
血糖の波が大きい
不安や焦りが抜けない
こういった
「配線側の乱れ」がある状態で、
ミトコンドリアを上げる・活性化する
という刺激だけを入れると、
エネルギーは増えても身体は楽にならず、
逆に、
ソワソワしたり
眠れなくなったり
落ち着かなくなることがあります。
これはサプリメントでも同じです。
COQ10
NMN
NAD+
これらは良い・悪いで分けるものではなく、
身体に入る「刺激」として捉えた方が
分かりやすいと思います。
刺激はその人の状態によって全く違う反応を起こします。
楽になる人
動きやすくなる人
呼吸が深くなる人
そういう方もいれば、
ソワソワする
目が冴えて眠れない
気持ちが落ち着かない
そうなる方もいます。
この違いは、
ミトコンドリアが良いか悪いかではありません。
多くの場合、
エネルギーが増えた分だけそれを制御する
神経・血糖・ホルモン・炎症の
バランスの弱さが表に出ているだけです。
発電量の問題ではなく、流し方の問題です。
身体は頑張らせるほど元気になるとは限りません。
むしろ、
静まる
緩む
抜ける。
そういう方向を求めていることも少なくありません。
整体でも
栄養でも
先ず大切なのは、
何かを足すことより邪魔を減らすこと。
流れが整えば、ミトコンドリアはこちらが意識しなくても自然に働き始めます。
ミトコンドリアは大切です。
でも主役ではありません。
主役は今この瞬間の身体の状態です。
本来ならば、
エネルギーは作り出すものというより、
整った状態から自然に湧き上がってくるもの。
そんなふうに捉えてみても
いいのかもしれません。^ ^
こんにちは!
今日のタイトルは、
若いうちから健康を意識したほうがいいの?
です。
これを正月明けの身体から考えてみてみましょう!^ ^
今日は1月3日です。
年末年始は、
食べすぎたり、飲みすぎたり、
知らん間に生活リズムが少し乱れた人も多いと思います。
まあでも、それでもいいんです。(^^)
お正月ですから。笑
ただ、ここでひとつだけ。
それは、
身体の感覚に目を向けてみてほしいんです。
例えば、
胃が重いとか、
体がだるいとか、
朝が起きにくいとか?
むくみやすくなってるとか。
これらは「失敗」ではなく、
実は、
身体がちゃんと反応しているサインです。
正直に言うと、
健康を意識するのは、
体を壊した時でも、
頑張る時でもなく、
こういう「ズレたあと」が
一番やりやすいはずです。
健康って、構造が
お金の投資と少し似ています。
一気に何かを変えなくても、
ほんの少し整えるだけで、
あとがかなり楽になります。
ただし、
身体の投資にはひとつ特徴があります。
それは、後戻りがしにくいということ。
若い頃は多少の無理がききます。
食べすぎても、
寝不足でも、
「まぁ大丈夫」と感じられるかもしれません。
でもそれは、
回復しているというより、
体力でカバーしているだけの場合が
ほとんどです。
体を壊してから始める健康対策は、
プラスを増やすというより、
マイナスを減らす作業になりがちです。
だからといって、
正月明けにストイックになる必要は
ありません。^ ^
いきなり食事を制限しなくていい。
無理に運動を始めなくていい。
「リセット」しようとしなくていい。
大事なのは、そう、
今の身体の状態をちゃんと感じてあげること。
「少し重たいな」
「ちょっと疲れてるな」
それに気づけるだけで、
身体は自然に元のリズムへ戻ろうとします。
でもどうせ健康を意識するなら、
「壊してから」ではなく、
「元気と不調の間」にいる今のうちに、、
が理想的かな。
年明けは、
何かを始めるより、
身体に耳を澄ませるのに
ちょうどいい時期ですね!
こんにちは。
前回の「日常生活の間」では、
行動や心の中にある“間”を見てきました。
本来なら次は「スペース編」へ
進むところですが、
その前に、少しだけ寄り道を。

今回は、生命そのものの中に流れる“間”
細胞の間を覗いてみたいと思います。
2025年のノーベル生理学・医学賞は、
大阪大学の坂口志文教授による
「制御性T細胞(Treg)」の発見に
贈られました。
免疫が暴走して自分を攻撃してしまう、
その暴走を静める「ブレーキ細胞」が存在するという発見。
免疫は強ければいいわけでもなく、
弱ければいいわけでもない。
生命が本当に求めているのは、最適な反応。
つまり「状態そのものの調和」なのです。
坂口先生の研究が示したのは、
免疫にも“間”があるということ。
細胞の中にも、
流れを止めず、
暴れさせず、
ただ“ちょうどいい呼吸”を保つ仕組みが
あるんです。
これは、整体の世界でいう
「ゼロ圧」や「中庸」とまったく同じ原理です。

白血球が暴走するとき、
その背後では神経が緊張しすぎています。
皮膚神経が過敏になり、
脳が興奮し、
副腎がストレスホルモンを出しすぎる。
それはまるで、
“存在が自分自身を守ろうとして、
自分を攻撃している”状態。
この構図は、
身体でも心でも、
社会でも、同じように起きています。
整体で皮膚へ適度な刺激を与えると、
神経は、
“安心して反応する”
という感覚を思い出します。
すると、
脳と副腎のやりとりが静まり、
免疫は再び本来のリズムで動き始めます。
免疫が「戦う」から「調う」へと相を変える。
つまり、
皮膚と神経を通して、
細胞のブレーキが静かに再起動していく。
坂口先生が発見した制御性T細胞(Treg)は、
まるで細胞の奥に眠る、
“ゼロの意識”のようです。

何もしないことで、
全体を整える存在。
それは沈黙の中で機能します。
整体もまた、
その“沈黙”に触れる行為だとしたら?
強く押すでも、操作するでもなく、
手と手のあいだに生まれる微細な“間”を通して、
神経と免疫が
ひとつの呼吸を取り戻していく。
だから、
免疫のバランスが整うとき、
それは単に炎症が消える
ということではなく、
存在そのものが、
“元の流れ”に戻るプロセスでもあります。

ノーベル賞の発見は、
医学がようやく“間”の存在を細胞レベルで見つけた瞬間だったのかもしれません。
それを科学は「制御」と呼び、
整体は「共鳴」と呼ぶ。
どちらも同じ方向を指しています。
過剰を鎮め、
欠乏を満たし、
全体をひとつに戻す。

“間”とは、
整うと整わないのあいだにある呼吸。
神経も免疫も、意識も、
その揺らぎの中で、
調おうとし続けている。
反応も、
努力も、
焦りもいらない。
ただ静けさの中で、
流れが思い出されていく。
治療とは、生命の調おうとする力に
同調する時間なんじゃないでしょうか?^ ^
こんにちは。
9月に入りましたが、
まだまだ夏が続いてますね。
今日は、何となく、
流れに乗るコツみたいな話をしたいと思います。
人間関係や体の不調や仕事やお金、
うまくいかないことが続くと、
どうしてもなんとかしなきゃ
と思ってしまいます。
早く治さないと、
もっと頑張らなきゃ!
どうにか変えなあかん!!
でも実はこのなんとかしなきゃ
という気持ちが、
体と心の流れを止めてしまうことがあります。
このとき意識は、
自分だけの力で何とかしようと働いていて、
肩や首は固まり呼吸は浅くなり、
神経もピリピリと過敏になっていきます。
頑張っているのに空回りしてしまう?
そんなときこそ立ち止まってみることが大切です。
そんな時にピッタリの表現が、
放っておく。
という言葉です。
これは諦めることでも、
無関心になることでもありません。
本当の意味は
小さな力で動かそうとするのをやめて、
大きな流れに任せてみる
ということです。
治そうと力を入れるほど体は固まり、
変えようとするほど心は緊張します。
でも一度ふっと手を放したとき、
呼吸が深くなり体の奥の流れが少しずつ戻り始めます。
施術でも大事にしているのが、
押しも引きもしないゼロ圧という考え方です。
ゼロ圧とはただ在ること、
頑張りも抵抗もない
ふわっと委ねているような状態です。
ゼロ圧に近づくと、
体はゆるみ神経や血流や呼吸の流れが自然に整い始めます。
うまくいかないとき、
悩みで頭がいっぱいのとき、
長引く不調にとまどうとき、
そんなときこそ結果をつかもうとする力を
一度手放してみる。
すると体は自分のペースを取り戻し、
本来持っている回復の力が動き出します。
心と体をしばるものの多くは
所有したいという思いかもしれません。
健康な体を持っていたい、
大切な人との関係を失いたくない、
安心できる未来を確保したい、
こうした気持ちはとても自然なことですが、
強く握りしめすぎると心も体も硬くなってしまいます。
一方で、
結果を所有しなくても大丈夫!
そう思えたとき
呼吸が深くなり体のこわばりがほどけていきます。
流れが自然に戻り始め
気づけば心も体も軽くなっていることに気づきます。
深呼吸をしてみる、
三回ゆっくり吸って吐くときは倍の長さで。
治さなきゃより体を信じてみようとつぶやく。
なるべく太陽や風や木や水など、
自然の流れに触れてみる。
こうして少しずつ
流れに委ねる感覚は体でつかめるようになります。
流れに任せるというのは
何もしないことでも諦めることでもありません。
小さな力で動かそうとするのをやめて、
体と心を大きな流れにゆだねたとき、
自然と呼吸が深くなり
神経や血流のリズムが整い、
不思議と体も心もラクになっていきます。
頑張っているのにしんどいと感じたときこそ
一度ふっと力を抜いて、
大きな流れに身を委ねてみませんか?
荻野接骨院では、
体に触れることで神経や血流の流れを整え、
心と体が大きな流れと再びつながるお手伝いをしています。
施術やカウンセリングを通して
結果を所有することから解放され、
本来の呼吸とリズムを取り戻すきっかけになればと思います。
こんにちは!
8月も最終日です。
今年は暑さが長く、全体的に身体は炎症が起こりやすくらなっていますが、
熱中症など注意したいです。
お若い方々は、頭から水シャワーなんかを浴びて、頭を冷やすと良いです。
それでは、
今日は腱鞘炎について、
少し深いお話をしたいと思います。
親指や手首が痛い、
物を持つのもつらい、
パソコン作業ができない、
こんなお悩みで来院される方は多いですが、
お話を伺っていると、
手首だけの問題ではないケースが
とても多いんです。
腱鞘炎は手首の使いすぎで説明されがちで、
それは当然ですが、
実際にはそれだけでなく、
いくつもの要素が重なって起きています。
まず医学的な視点から見ても、
手首の動きは頚椎、横隔膜、呼吸などと深くつながっています。
首や肩の緊張によって神経や血流が滞れば、
炎症は長引きます。
肝臓の働きや血液の質も関係しますし、
女性ホルモンや副腎の機能が影響していることもあります。
さらに、重心の崩れや姿勢の問題で、
本来なら肩や体幹で分散されるはずの力が
手首に集中することもあります。
つまり、
痛い場所だけを見ても本質には届かないのです。
ここで大切なのは、
使いすぎた結果ではなく、
なぜ使いすぎてしまったのかという視点です。
腱鞘炎で悩む方を見ていると、
体に負担がかかっているだけでなく、
休めない意識が背景にあることが
多いと感じます。
もっと頑張らなきゃいけないから、
迷惑をかけられないから、
結果を出さなきゃいけないから、
ちゃんとやらなきゃいけないから、
こうした無意識の想いは、
体を休ませることを許さず、
手を止められないまま動き続けさせます。
結果として、
限界を超えているのに
力を抜けない状態をつくり、
手首に過剰な負荷がかかっていきます。
そして、身体と概念はつながっています。
手を握りしめると、
肩や首、横隔膜まで連動して硬くなります。
逆に手をゆるめると、
呼吸が広がり、
神経も落ち着きます。
腱鞘炎は、
手を握るという動きの中で起きていますが、
その奥には「手放せない意識」が
隠れているかもしれません。
抽象的に見ると、
症状は敵ではなくサインです。
腱鞘炎は、
もうそんなに強く握らなくてもいい、
もっと委ねてもいいというメッセージかもしれません。
痛みは不快なものですが、
その奥に解放や変化への扉が
隠れていることがあります。
腱鞘炎をきっかけに、
多くの方が最終的に気づくのは、
自分の生き方のパターンです。
頑張り続けること
休むことへの罪悪感。
もしくは与えることを優先しすぎていること。
手首の痛みは、
このまま握りしめて進むのか、
それとも少し手をゆるめてみるのか、
という問いかけかもしれません。
あなたは今、
何をそんなに強く握りしめていますか?
もしその手をふっと開いたら、
どんな世界が広がるでしょうか?
これしかないという、
正解はありません。
腱鞘炎は単なる手首の炎症かもしれません。
でもその奥では、
生き方や概念や意識がそっと動いています。
それに気づいたとき、
痛みよりも深いところから
変化が始まるかも知れませんね。^ ^
こんにちは。

今日のお話は、花粉症は「敵」か?
はたまた身体の声か?
かゆみって?
です。
まだまだ花粉症(環境汚染症)の季節。
鼻水、くしゃみ、かゆみ…
「なんでこんなに反応するんやろ」
って、
つらくなることもあるある?
でも、
その裏側には身体が、
一生懸命やっていることがあるんです。
先ずは復習にもなりますが、
ヒスタミンは“悪者”じゃないってこと。
ヒスタミンって聞くと、
「アレルギーの元」
「かゆみの原因」って思われがち。

でも実は、
ヒスタミンには大事な役割があるんでした。
• 異物を排除する警報係(免疫)
• 胃酸を出して消化を助ける
• 脳内では覚醒を保ち、集中力に関わる
• 炎症を起こして、修復を始めさせる
つまり、
ヒスタミンは身体を守るための味方でした。
ただ、
出すぎたり、
分解がうまくいかなかったときに
“暴走”するだけなんです。
そして、
ヒスチジンとヒスタミンの関係です。
ヒスタミンの材料になるのが
「ヒスチジン」という魚に多いアミノ酸。
(肉食が原因って言う仮説はこれ。)
ただ、ヒスチジンは、
筋肉の材料になったり、
抗酸化物質(カルノシン)になったりと、
本来とても大事な栄養素ですね。

ちなみに筋肉以外に、神経や細胞やホルモンなど、身体のほとんどは
タンパク質からできていますよ。
そして、Tレグ細胞を覚えてますか?
Tレグ細胞(制御性T細胞)は、
免疫の世界でいう「ブレーキ役」。
アレルギー体質の人は、
このTレグが少なかったり、
働きが弱いことが多いんでしたね。
そしてTレグがしっかり育てていると、
ヒスタミンの反応も穏やかになります。
Tレグ細胞を育てる栄養素や生活習慣に、
ビタミンD、ビタミンC、オメガ3、亜鉛、マグネシウム、プロバイオティクス
が必要で、
何より腸内環境の改善
は土台となり、
出来れば、動物として、
自然とのふれあい・ストレスケア
がありましたね。

では、
かゆいのを掻くとなぜ悪化するのか?
ですが、
誰もが痒みは掻くとその瞬間、
一時的に気持ちいいです。
何故なら脳内ドーパミンやエンドルフィンなど快楽物質がでるから。
でもそれは、
ヒスタミンもが、
さらに出てしまうきっかけにもなるんです。
• 掻く→皮膚が刺激される→ヒスタミンが追加放出
• ヒスタミン→血管拡張・神経刺激→かゆみが悪化
• 掻く→また出る…というスパイラルに。

それでも掻くことには、
意味があるのでしょうか?
実は掻くことで、
一瞬の安心感や快感を得て、
感情や不安を逃がして、
身体とのつながりを取り戻しているです。
更に、
掻く=「自分を撫でる」ことで、
迷走神経を整えて、
緊張を解放しようとしていたり。
掻くこと自体が「悪い」じゃなくて、
掻くことで何を補ってるのか?
何を感じたいのか?
そこに耳を傾けることが、
大きなケアになるんですね。

例えば、
まぶたを掻いたり、
触れる意味。
まぶたって、
全身で最も皮膚が薄く、
神経が豊富な所。
それは交感神経が豊富でもあり。
そこを掻いたり触れるのは、
刺激から自分を守ろうとする反応
安心したい、
情報から離れたいという無意識の声
(あくまで無意識の話。
意識は勘違いした欲求不満があったりもするので、情報を見るわけです。)
眠気、疲れ、内にこもりたいサイン
だったりもあるかも知れません。
そして
それでも「見ること」に疲れた身体が、
「ちょっと目を閉じさせて」と、
言ってるのかもしれません。
「もう休みたい」
「自分の中に戻りたい」ってサイン
※赤ちゃんが眠いとき目をこするのもこれと同じ。

どうしても掻きたい時は、
その前に、
因みに手で目を覆ったり、
アイマスクをしたり
なんかはオススメですね。
“掻く”じゃなくて“覆う・包む”という、
手や物の使い方によって、
まぶたと神経の安心スイッチが入りますから。
後は冷やしたり、
トントンと圧を加えたり、
圧迫したりも良いですね。
それでも掻いてしまうなら、
それを観察してみましょう。^ ^
と、言うことで、
かゆみは“邪魔”じゃなく“メッセージ”でもありました。
花粉症、かゆみ、
まぶたを掻くこと、
それらはすべて、
今の状態を映し出しているメッセージ。

ヒスタミンもTレグも、
私たちの身体を守り、
整えようとしている存在です。
「反応する身体」=「生きている身体」
そう思えると、
ちょっと見え方が変わってくるかもしれません。
こんにちは!
最近、血圧について、
相談を受けることが続いていたので、
簡単に書いておきます。

高血圧とか言われると、
「病院に行くべきかな…」
「薬を飲んだ方がいいのかな…」
そう不安になる方も多いと思います。
もちろん、
必要に応じて病院で診てもらうことは、
大切です。

でもその前に、
ちょっと別の視点から“血圧”について考えてみるのも、
意外と役に立つことがあります。
例えば、こんな問いかけです。
「血圧って、そもそも何だろう?」
高血圧で心配なのって、「血管内の圧による心臓の負担」ですよね。
身体はどうして血管に圧をかけるんでしょう?
血液って、
酸素や栄養を全身の細胞に
届けるために流れてます。
だから、しっかり届けるために
必要があるから圧を上げてでも
流そうとしてるんです。
「おい、もっと早く届けろ!」って、
心臓に細胞が指令を出してるような感じ。
じゃあ、
「どうしてそんなに急いでるんだろう?」
「どこにそんなに届けたいんだろう?」
って考えてみると、
身体が教えてくれることがあるかもしれません。
「血圧が高くなる必要って?
どんな理由がある?」
血圧は、
ただ「高いから下げればいい」
ものじゃなくて、
「上げる理由があるから、上がっている」
ものでもあります。
例えば、
・体が冷えてて末端に血を送らないといけないのかもしれない
・どこか血流が滞っていて、押し流そうとしているのかもしれない
・「もっと頑張れ!」って、自分自身に圧をかけてるのかもしれない
油物が悪くて血管が硬くて、、、
血管を流れる赤血球が成長していなくて、、、
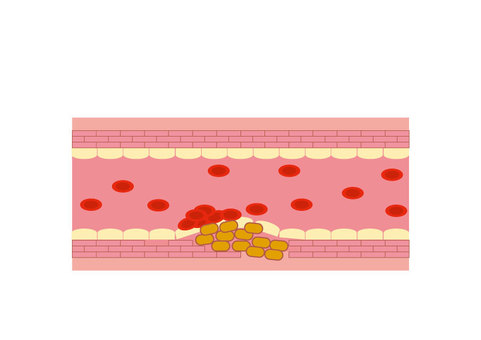
あるいは、
「心」に圧がかかっている場合もあります。
仕事のこと、家庭のこと、
無意識に
「こうしなきゃ」「こうあるべき」って、
力が入っていることはありませんか?
もしかすると、
「血の圧」は「家族の圧」かもしれないし、
「生活の圧」かもしれません。
身体は、
「気づいてほしい」って、
サインを出してくれているのかもしれません。

「どんな状態になりたいんだろう?」
薬で下げることも時には必要ですが、
本当に望んでいるのは、
ただ数字を下げることじゃなくて、
「安心して、楽に暮らせること」
「ホッとして、気持ちよく過ごせること」
じゃないでしょうか?
じゃあ、
「力を抜ける時間って、
どれくらいあるかな?」
「ホッと息をつける場所って、
ちゃんとあるかな?」
そんなふうに、
自分に問いかけてみると、
血圧の数字だけじゃなく、
自分の身体や心との
向き合い方が変わってくるかもしれません。

血圧を下げるために、
できることは?
数字に一喜一憂するよりも、
まずは、
こんなことを試してみませんか?
● 深く息を吐く時間をつくる
● 肩や首を温めて、ゆるませる
● 手や足をさすって、「よく頑張ってるね」と声をかける
● 「こうせねば」ではなく、
「まぁ、いいか」と言える瞬間を増やす
そんなふうに、
自分にかけていた「圧」を
少し緩めることで、
身体も
「もう無理に上げなくてもええんやな」
と感じて、
自然とバランスが整っていくこともあります。

症状=「身体からの手紙」
血圧が高いというのも、
「身体からの手紙」みたいなものです。
「ちょっと気にかけてくれる?」
「今、こんな感じになってるんやけど」
そんなふうに、
身体が話しかけてくれてる。
その声に耳を傾けて、
無理に押さえつけるんじゃなく、
「そうか、教えてくれてありがとう」
って、
ちょっと優しく向き合ってみる。
そんな時間が、
結果的に、一番の薬になるのかもしれません。

先ずは今日も、
無理せず、ゆるゆると。
すこやかに。^ ^
こんにちは。(^^)
本日は立春。
暦の上で春の始まりとされる日。
寒さがまだ残るとはいえ、
ここから徐々に春の気が満ちていきます。

昔の日本では、
立春を一年の始まりと考えていて、
旧暦ではこの日から新しい年が始まるとも言われていました。
豆まきをする節分も、
もともとは「立春の前日」であり、
「新しい季節に向けて、不要なものを祓う」
意味が込めていたみたいですね。

まあそれもさらに古代に遡ると、
意味は変わってきますが。
今日は、
痛みが教えてくれるもの
と言う視点のお話です。
整体の施術をしていると、
痛みを抱えて来院される方の多くが、
「痛みをなくしたい」
と言われます。
一般的には当然のことですね。
痛みは不快で、
日常生活に支障をきたすもの。
というのが常識だと思われてますから。
ですが、
「痛みを取り除く」ことよりも、
痛みが
何を伝えようとしているのか?
を、
感じ取ることも、
とても大事な視点になります。

実は痛みは、
単なる肉体の現象ではなく、
流れが滞った結果
として現れるものだからです。
それは、
筋肉や関節の滞りだけでなく、
自立神経の滞り、
心の滞り、
人生の流れの滞り
ともつながっています。
そう
「痛みを消す」だけでなく、
「流れを思い出す」を選択の一つに
持って頂きたいかな。

多くの人は、
痛みを「悪いものや、敵」だ
と考えます。
ですが、
痛みは自然物であり、
最大の味方である身体が、
全てのバランスを取り戻そうとする力の
表れでもあります。
例えば、
長年の肩こりがある人。
その人が抱えているのは、
単なる筋肉の問題ではなく、
「力を抜くことを忘れてしまった身体」です。
無意識のうちに緊張し、
肩を上げ、頑張り続けている。
「本当は、もう力を抜いてもいいのに」
身体はそう伝えたいのかもしれません。

整体を通して
身体の詰まりをほどいていくと、
ある瞬間、
フッと気づくことがあります。
「あれ? こんなに楽に息ができたんだ」
「こんなに腕が軽かったんだ」
それは、
ただ筋肉が緩んだだけではなく、
意識の奥にあった力みが解放された瞬間です。
痛みは「出口」でもある。
整体に来られる方の中には、
施術を受けている最中や後に、
「涙が出そうになった」
「なんだか心が軽くなった」
と言われる方もいます。
それは、
痛みが出口になった瞬間。

身体に滞ったものが、
感情や思考とともに流れ出す。
身体は、本来の動きを取り戻す。
意識もまた、それに呼応する。
痛みは、
「ここで何かが滞っている」
というサインであり、
そこに気づいたとき、
流れは自然と戻っていきます。
流れに乗るためにできること。
整体は、
単に「歪みを整える」もの
ではなく、
「流れを思い出す」ための
時間でもあります。

痛みを感じたとき、
まずはこう問いかけてみてください。
「これって何?」
「今、どこで力んでいるのだろう?」
「何を守ろうとして、この痛みを感じているのだろう?」
「もし、この痛みが教えてくれていることがあるとしたら?」
そうして身体の声に耳を傾けると、
痛みは「消すべきもの」ではなく、
「対話すべきもの」に変わります。
整体を受けることは、
ただ身体を整えることではなく、
意識の流れを取り戻すことでもあります。
痛みを通して、
あなたの身体が何を
伝えようとしているのか。
それを感じることで、
身体の流れも、
人生の流れも、
より軽やかになっていくかもしれません。
^ ^
みなさんこんにちは。
寒暖差が大きくて、
鼻水や咳をする人が増えてますね。

この寒暖差アレルギーは、
どういったものなのでしょうか?
寒暖差アレルギーとは、
正式な医学用語ではなく、
急激な気温の変化によって霊長類にとっての
絶対温度36.5度を保つために、
自律神経がフル稼働になり、
生命力が敏感になっている状態です。
敏感なので、ちりほこりや、繊維、邪気など、様々なものに反応しやすくなります。

それらを排出させようと、
くしゃみから鼻水、
鼻づまりから、目のかゆみ、
更にはなんとなく倦怠感を、
と、
花粉症や風邪に似た症状が現れます。

現在人にはなかなか難しいですが、
日頃の習慣から、
夜更かしや食の乱れなどを気をつけておかないと、
知らぬ間に
上部の胸椎、菱形筋などについた背骨が硬くなり、
自律神経が弱っている場合には、
硬さはなかなか改善せず、
アレルギー反応が悪化しやすいです。

それでは、
対処法と予防法としては何があるでしょうか?
先ずは、
部屋や外出時に、
体温調節を意識する事。
例えば、急激な気温変化を避けるため、
脱ぎ着しやすい服装を選んだり。
オススメは、
マフラーやストール。
後はレッグウォーマーなど。
これらがあると少し寒暖差を和らげます。
根本的には
自律神経を整えること。
すなわち、やりたいことがあっても、
規則正しい生活を心がけ、
なるだけ十分な睡眠を取る。

そして、
これは師匠や先生となる人がいないと難しいですが、
人生マインド、哲学から、
思考、感情の扱い方を学習し、
リラックスできる時間を増やしいく。
他には、
簡単なことでは、
鼻への刺激を軽減するために、
マスクを使用して、
外気の冷たさを緩和するとか、
アロマオイルの、
ペパーミントや、ベルガモット、
ユーカリなどをマスクに落としたり、
部屋に使うと呼吸が楽になりますよ。^ ^
上部の背骨を柔らかくするのも整体的なアプローチとしてありです。
最後に、よくある質問から、
いつまでも若さを保つ秘訣をご紹介します。
ほんとによく聞かれるのでね。笑
若さや健康で大事になってくるのは、
からだへの意識、
からだとの関係性です。
私のからだなんやから、
私の好きにしてもいいやん。
私の勝手やん。
私の好きなものを食べて、
私の好きなように生きていく!
私のものなんやから、
私が楽に生きていく。
って
考えの人は早く老けます。

逆に、
私とからだ。
からだに私は入ってなくて、
実は空だ。
私とからだはべつのもの。
からだは自然物。
からだは借りも何だから、
からだが求めているものや、
からだが欲している時間や空間や刺激を
私が提供してあげようと、
思える優しい人は、
いつまでも若々しくいられます。

まあこのブログを読むような方は、
きっとわかってましたよね。^ ^
こんにちは。
11月に入り、
アメリカでは大統領選挙ですね。
日本はアメリカと一蓮托生な感じですから、
結果次第で、大きく流れが変わりそうですね。

先日のことですが、
沖縄空手のサイという武器がありまして
結構重く硬い金属で、
それが生徒さんとの個人レッスン中に、
左手に当たり、

結構の痛みが出たのですが、
直ぐテーピングと包帯で治療することで、
翌日は痛みは引き、
普通に動かせれる状態であれました。
いやーぁ、
包帯はすごいなと。
今日は包帯について、
巻くだけで身体がラクになるワケを
お伝えします。
え?包帯って、
「ただ巻くだけで効果あるん?」
って思う人が多いかもですが、
実はかなり奥が深いですよ。
打撲やケガで包帯を巻くときに
知っておきたいポイントや、
プロでも意外と知られてない
包帯の効果について、書いてみますね、

その1は、
まずは圧迫効果だけじゃない
流れをサポートする役割がある!
包帯の基本的な役割としては、
患部を「適度に圧迫すること」で痛みを和らげることですが、
実は巻くことで、
血液やリンパの「流れ」をサポートしてくれる役割があります。
体はケガした場所に
血液を送り込んで治そうとしますが、
逆に血流が詰まると腫れや痛みがひどくなります。
それを包帯を巻いて、
「適度な圧」で流れを保つことで、
血液うっ血を防ぎつつ、
体の自己修復力をサポートしてくれるわけです。

次にその2、
あまり知られてないですけど、
包帯を巻くことで「神経」も落ち着かせることができます。
ケガしたとこって、
神経が過敏になりやすいんですが、
それが痛みを強く感じさせる原因にもなります。
包帯を巻くことで、
神経に「ここ大丈夫やで」
っていうサインを送ることができるんです。
この「神経を落ち着かせる」効果は、
特に打撲や筋肉の痛みで効果が出やすく、
ふんわり包むことで、
余計な痛みを減らしてくれるから、
包帯が「メンタル面でもサポーター」
になってくれる訳です。

その3、
包帯の素材としてよく使われる綿は、
保温性があり患部をじんわり温めてくれます。
温めることで血行が良くなって、
体が自然に「治そう」とする自己治癒力が高まります。
例えば慢性的な痛みがあるときや、
冷えによる痛みがある人には、
包帯の温かさがすごい効果を発揮したりします。
温泉とかサウナに入ると体が楽になるのと同じように、
包帯で温もりを与えることで、
体をリラックスさせ、
痛みを減らすことができるんですね。

その4.
また包帯って、
ただ巻くだけでなく、
実は巻き方によっても効果が変わってきます。
例えば、
少し強めに巻くときは「クロス巻き」をすると、しっかりサポートできるし、
動きを制限したいときには「八の字巻き」が適してます。
あと、
包帯の端っこを軽く折って「厚み」を出すことで、
関節部分のサポート力が増したりします。

その5、
最後に、
包帯は「皮膚」の代わりになる?
ケガしたところは皮膚が傷ついてますから、
外からの刺激にも弱くなっています。
包帯は、
その「第二の皮膚」として外からのダメージを防いでくれ、
ほこりやばい菌から守るだけやなく、
風が当たったときのチクチクする痛みも、
包帯が和らげてくれます。
この「保護効果」は、
特にケガした直後や、
まだ痛みが強いときに助かりますね。
包帯が「バリア」として機能することで、
ケガの治りがスムーズに進むわけです。
包帯の役割って思ってた以上に奥深いですね。

ただの布じゃなく、
体と心を支える「サポーター」として、
ケガしたときに頼りになる存在。
みんなさんもケガしたときは、
ぜひこの包帯の効果を思い出してみて下さい。^ ^




























































