Blog記事一覧 > 院長の考え方 | 淀川区・十三で評判の荻野接骨院の記事一覧
こんにちは!^ ^
前回のブログは主婦層から良い反響がありました。
ありがとうございます。
そこで更にオススメの商品を
こちらでもお伝えします。
それは、
電波遮断携帯圏外ポーチ
ってやつです。

こちらはスマホをいれるポーチなんですが、
入れてるだけで、
電磁波を遮断し、
圏外状態にしてしまいます。
しかも、出し入れが面倒くさいので、笑
スマホを触る時間が
結果的に減りますし、
目覚ましがわりに使っている方も、
この中に入れていれば、近くに置いてても大丈夫。
更にスマホ依存が減少した結果、
前頭前野の働きが爆上がりするようです。
40歳以降の人には癌や、認知症など、
様々な病気予防にもなりますね。
では、今日は運の流れについて。

まあ、何度かこのテーマについては書いてますが、
また違った角度から書いていきたいと思います。
はじめに、
1.「運がいい・悪い」とは?

「運がいいですね」「最近ツイてないな…」
日常の中で、こんな言葉を耳にすることがありますよね。
でも、運とは本当に
「持っている」「持っていない」
といったものなのでしょうか?
もしかすると、
運は「自分で掴みにいくもの」ではなく、
「巡るもの」 かもしれません。
整体でも、
身体が緊張して硬くなっていると、
血流やエネルギーの巡りが悪くなり、
痛みが生じます。
逆に、
適度に緩み、
巡りが良い状態だと、
自然と身体が軽くなります。
運もそれと似ているのではないでしょうか?
「流れに乗ること」こそが、
運と上手く付き合うコツかもしれません。
2. 「巡り」があるところに、運がやってくる?
運が良いと感じるとき、
多くの人は「タイミングが良かった」
「流れがスムーズだった」と話します。
逆に、運が悪いと感じるときは、
「停滞している」「詰まっている」ように
感じることが多いです。
これも、整体の施術と似ています。
✔ 筋肉が硬くなり、血流が滞ると痛みが出る。
✔ でも、緩んで流れが生まれると、自然と身体が楽になる。

運もまた、
「流れ」を大切にすると、
無理に掴みにいかなくてもやってくるものなのかもしれません。
「もっと運を良くしたい!」と焦ると、
かえって流れが滞ることもあります。
無理に運をコントロールしようとするよりも、
「今、自分の流れはどうなっているか?」
と観察することが、
運の巡りを良くする第一歩
なのかもしれません。
3. 「緩み」がないと、運も滞る
日常の中で、ずっと緊張した状態でいると、
身体がカチカチに固まり、
動きづらくなります。
これもや、運の流れとも関係しています。
✔ 「やらなければならないこと」に追われすぎると、余裕がなくなる。
✔ 「こうしなければならない」という思いが強いと、視野が狭くなる。

そんなときこそ、一度立ち止まって、
「緩み」をつくってみることが大切です。
✔ 深呼吸をする
✔ 何も考えず、ただお湯に浸かる
✔ ふと空を見上げてみる
このような「緩み」の時間を作ることで、
心と身体に「隙間」が生まれます。
4. 「隙間」が運を引き寄せる
水が流れるためには、道が必要です。
でも、その道が塞がれていたら、
水は溜まってしまいます。
運も同じで、
「隙間」がないと流れ込んできません。
✔ スケジュールが詰まりすぎていると、新しい出会いのチャンスがない。
✔ 頭の中が「やるべきこと」で埋め尽くされていると、ひらめきが生まれない。
逆に、少し予定を空けたり、
何も考えない時間をつくることで、
ふとした瞬間に、
運の流れが変わることがあります。
整体でも、
ガチガチに力が入っている人より、
適度に緩んでいる人の方が、施術の効果が出やすいです。

運もまた、「隙間がある人」 に、
スッと流れ込んでくるのかもしれません。
5. まとめ:「運は流れに任せるもの」
✔ 運は「持つもの」ではなく、「巡るもの」
✔ 緩みがないと、運の流れも滞る
✔ 隙間をつくることで、運が入りやすくなる
運が良いか悪いかを気にしすぎるよりも、
「今、流れを感じているか?」
を意識することが、
運を引き寄せるコツなのかもしれません。

この瞬間、
ほんの少しでも「緩み」や「隙間」を
意識してみる時間をつくってみませんか?
換気するだけでも。
そうすることで、
ふとしたタイミングで、
思いがけない「運の流れ」に気づくかもしれませんよ。(⌒▽⌒)
こんにちは。
二月も末に入り、
寒さが温かくなってきましたね。
こうした寒暖差をきっかけに、
くしゃみ、鼻づまり、目のかゆみ…
今年はついにデビューなのか?
と花粉症を自覚する人が増えているようです。
実は、
花粉症になりやすい体質には、
おもしろい共通点があります。

その一つが 「歯茎の腫れ」。
食べ物がやたらと奥歯に
挟まるなら要注意。
歯茎がむくんでいるサインであり、
それは全身の粘膜にも影響を与えます。
鼻腔の粘膜がむくめば、
花粉症の症状が悪化。
さらに、
小腸粘膜のむくみは栄養吸収を妨げ、
免疫バランスを崩します。
この時期こそ、
食べ方を見直すチャンスにしてみては?
気がつけば早食いに戻ってしまったあなた!
唾液をしっかり出しながら、
ゆっくり噛んで食べることで、
春本番の花粉症リスクを抑えましょう。
早食い、
大食い
かっこみ食いは、もちろん、
おやつや甘いものには特に注意を。
そのまま体内水分の
クオリティの低下を招き、
慢性鼻炎症状につながりやすくなります。
ちょうど寒さと温かさの変換のいま、
カラダの中の水分代謝
変容期にあるため、
リンパの流れ方が変わったり、
消化液の出方が多くなったりしやすい時期ですから、。
水分代謝の変わり目は、
いつもより胃の膨らみが大きいと認識しつつも、
なんだか食べて溶かしたいモードになって、
ついおなかの中を満たしてしまいたくなるのです。
結果すごい肩こりを感じ易くもなります。
それでは本題の、
料理とは「場」と「エネルギー」を
繋ぐものとは?
意識が料理に与える影響とは?
について。

みなさんは、
「昔の料理の方が美味しく感じた」
「同じ料理なのに、作る人によって味が違う気がする」
などと、思った経験はありませんか?
実は料理は、
単なる栄養補給ではなく、
「場」と「エネルギー」が繋がるものでもあります。
それは、
どこで、誰が、どのような意識で
作るかによって、
その料理が持つエネルギーが
変わることがあるからです。
今回は、
料理のエネルギーに影響を与える
要素についてお話しします。

1. 料理は「場のエネルギー」を映す
料理は、作られた場所の
雰囲気や空気感をそのまま映し出します。
例えば、
• 家庭の食卓で作られる料理
→ 家族の温かさや安心感が加わる
• お祭りの屋台の料理
→ 活気や楽しさのエネルギーが入る
• 禅寺の精進料理
→ 静寂や落ち着きの気が宿る
また、
神社では「直会(なおらい)」といって、
神前にお供えした食べ物を
下ろしていただく風習があるのは
ご存知かと思います。
これは、
神聖な場のエネルギーを
体に取り込むという意味があり、
普通の食事とは違う
特別なものとされています。
このように、
料理は作られた場所での
エネルギーを受け継ぎ、
それを食べる人へと伝えているのです。
2. 作る人によって料理のエネルギーは変わる?
同じ料理でも、
「誰が作るか」によって
エネルギーが変わることがあります。

これは、
作る人の意識や気持ちが料理に影響を与えているからです。
① 陰陽の視点から見る「料理を作る人のエネルギー」
陰陽の考え方では、
男性(陽)と女性(陰)では
エネルギーの性質が異なります。
そのため、同じ料理でも、
作る人のエネルギーによって
次のような違いが生まれるかもしれません。

作る人 エネルギーの傾向と、
料理の特徴には、
男性(陽)
活性化、
動きを生み出す 力強く、
刺激がある
女性(陰)
安定、落ち着き、
包み込む 優しく、
癒しのある
例えば、
• 「おばあちゃんの味噌汁」
は落ち着く(陰のエネルギー)
• 「シェフが作るフレンチ」
は気分が高まる(陽のエネルギー)
これは、
料理自体が持つエネルギーに、
作る人のエネルギーが加わることで
起こる現象かもしれません。
チェーン店の牛丼屋でも、
結構はっきりと違いが出ますね。
② 「作るときの意識」が料理に与える影響
料理は、作る人の気持ちや
意識が反映されるものです。
• 急いで作った料理と、
丁寧に作った料理では、
同じ材料でも味が違うと感じることがあります。
• 「美味しくなれ」
と思いながら作る料理と、
義務感で作る料理では、
食べたときの満足感が変わったり。

実際、
日本には「手当て」という言葉があるように、手から気(エネルギー)が伝わると考えられています。
料理も同じで、
作るときの意識の質が、そのまま食べる人に影響を
与えるのかもしれません。
3. スマホ時代の料理はエネルギーが変わった?
最近ふと、
「スマホがなかった頃の料理の方が、味にエネルギーがあった気がする」と
思うことがありました。
これは、
料理を作るときの「意識の集中度」が
関係しているのかもしれません。
① 「ながら料理」と「集中して作る料理」の違い
現代では、スマホを見たり操作しながら
料理することも増えていますね。
しかし、これは言い換えれば
「意識が分散している状態」です。

料理の仕方と、意識の状態 。
料理のエネルギーとは?
スマホを触りながら作ると、
意識が分散 エネルギーが弱まる?
料理に集中して作る
意識が純粋 料理の質が高まる?
古の禅の教えに、
「一行三昧(いちぎょうざんまい)」
という言葉があります。
これは、
「何かをするときは、
その行為に完全に集中する」
ことを意味します。
料理に集中することで、
食材の香り、音、手触りを
感じながら作ることができます。
その結果、
料理自体に込められるエネルギーが高まり、食べたときの満足感も変わるのかもしれません。
子供などが母親の料理を食べない家庭の背景には、
このエネルギー問題もあるかもしれませんね。
4. 「料理は場とエネルギーを繋ぐもの」
と意識すると食事が変わる?
ここまでの話をまとめると、
料理は単なる食べ物ではなく、
「場」と「作る人のエネルギー」を
繋ぐものだと言えます。

食事をする際に、
こんな視点を持ってみるのも
面白いかもしれません。
✅ どんな場で食べるか?
→ 家庭、神社、外食、旅先…食べる場所のエネルギーを感じてみる
✅ 誰が作った料理を食べるか?
→ 手作りか、工場生産か…作る人のエネルギーを意識してみる
✅ どんな気持ちで作られたか?
→ 料理する人の意識が、味やエネルギーに影響を与えている
これらを意識するだけで、
普段の食事の感じ方が変わるかもしれません。
「食べること=その場のエネルギーを体に取り込むこと」
だと考えると、
料理に対する向き合い方も、
少し変わるのではないでしょうか。

最後に…
今回のテーマは、
ふとしたチェーン店での、
「味の違い」に対する気づきから
生まれました。
皆さんも、
最近の食事で「何か違う」と
感じたことがあれば、
ぜひ意識を向けてみてください。
料理は、場と人を繋ぐもの。
毎日の食事が、
より豊かで心地よいものになりますように。
^ ^
こんにちは!
最近、血圧について、
相談を受けることが続いていたので、
簡単に書いておきます。

高血圧とか言われると、
「病院に行くべきかな…」
「薬を飲んだ方がいいのかな…」
そう不安になる方も多いと思います。
もちろん、
必要に応じて病院で診てもらうことは、
大切です。

でもその前に、
ちょっと別の視点から“血圧”について考えてみるのも、
意外と役に立つことがあります。
例えば、こんな問いかけです。
「血圧って、そもそも何だろう?」
高血圧で心配なのって、「血管内の圧による心臓の負担」ですよね。
身体はどうして血管に圧をかけるんでしょう?
血液って、
酸素や栄養を全身の細胞に
届けるために流れてます。
だから、しっかり届けるために
必要があるから圧を上げてでも
流そうとしてるんです。
「おい、もっと早く届けろ!」って、
心臓に細胞が指令を出してるような感じ。
じゃあ、
「どうしてそんなに急いでるんだろう?」
「どこにそんなに届けたいんだろう?」
って考えてみると、
身体が教えてくれることがあるかもしれません。
「血圧が高くなる必要って?
どんな理由がある?」
血圧は、
ただ「高いから下げればいい」
ものじゃなくて、
「上げる理由があるから、上がっている」
ものでもあります。
例えば、
・体が冷えてて末端に血を送らないといけないのかもしれない
・どこか血流が滞っていて、押し流そうとしているのかもしれない
・「もっと頑張れ!」って、自分自身に圧をかけてるのかもしれない
油物が悪くて血管が硬くて、、、
血管を流れる赤血球が成長していなくて、、、
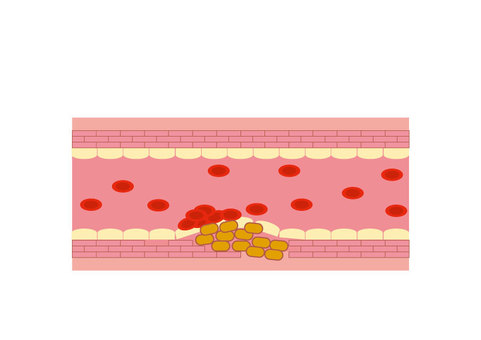
あるいは、
「心」に圧がかかっている場合もあります。
仕事のこと、家庭のこと、
無意識に
「こうしなきゃ」「こうあるべき」って、
力が入っていることはありませんか?
もしかすると、
「血の圧」は「家族の圧」かもしれないし、
「生活の圧」かもしれません。
身体は、
「気づいてほしい」って、
サインを出してくれているのかもしれません。

「どんな状態になりたいんだろう?」
薬で下げることも時には必要ですが、
本当に望んでいるのは、
ただ数字を下げることじゃなくて、
「安心して、楽に暮らせること」
「ホッとして、気持ちよく過ごせること」
じゃないでしょうか?
じゃあ、
「力を抜ける時間って、
どれくらいあるかな?」
「ホッと息をつける場所って、
ちゃんとあるかな?」
そんなふうに、
自分に問いかけてみると、
血圧の数字だけじゃなく、
自分の身体や心との
向き合い方が変わってくるかもしれません。

血圧を下げるために、
できることは?
数字に一喜一憂するよりも、
まずは、
こんなことを試してみませんか?
● 深く息を吐く時間をつくる
● 肩や首を温めて、ゆるませる
● 手や足をさすって、「よく頑張ってるね」と声をかける
● 「こうせねば」ではなく、
「まぁ、いいか」と言える瞬間を増やす
そんなふうに、
自分にかけていた「圧」を
少し緩めることで、
身体も
「もう無理に上げなくてもええんやな」
と感じて、
自然とバランスが整っていくこともあります。

症状=「身体からの手紙」
血圧が高いというのも、
「身体からの手紙」みたいなものです。
「ちょっと気にかけてくれる?」
「今、こんな感じになってるんやけど」
そんなふうに、
身体が話しかけてくれてる。
その声に耳を傾けて、
無理に押さえつけるんじゃなく、
「そうか、教えてくれてありがとう」
って、
ちょっと優しく向き合ってみる。
そんな時間が、
結果的に、一番の薬になるのかもしれません。

先ずは今日も、
無理せず、ゆるゆると。
すこやかに。^ ^
こんにちは。^_^
2月11日は建国記念日でしたね。
この日で日本は2681歳になるようで。
神武天皇が即位された日本の始まりと言う日でした。
今日は栄養や整体では中々扱えない、
思考、感情、哲学の部分から、
人生の課題の一つの
仕事について、
書いてみます。
たぶん、
人は誰もが「天職」を求めて生きています。

だけど、
「本当にやりたい仕事って何だろう?」
「これが天職なのか?」
と迷うことも少なくありません。
多くの人が思い描く天職は、
才能を活かし、
評価され、
やりがいを感じるもの。
ですよね。
でも、
それが本当の「天職」でしょうか?
今回のブログでは、
自分の枠を超えた視点から「天職」を考えてみたいと思います。
ただの職業としての天職ではなく、
存在そのものとしての
仕事の在り方に目を向けてみましょう。

1. 目指す天職と、
自然にたどり着く天職
まず、
「天職」と一言で言っても、
その捉え方には
大きく二つのアプローチがあります。
目指す天職とは?
これは多くの人が
思い描く天職のイメージです。
• 才能を活かせる仕事
• やりたいことをしている感覚
• 評価されることで満たされる欲求
• ワクワク感や達成感

これらは一見魅力的ですが、
同時に
「もっと上を目指さないと」
「評価されないと価値がない」
というプレッシャーが生まれることもあります。
求めれば求めるほど、
逆に「足りない」
という感覚が大きくなってしまう
こともあるのです。
自然にたどり着く天職とは?
一方で、もう一つの天職の形は、
力まず自然に続けられるものです。

• 努力や計画を超えて、
自然に流れるように続けられる仕事
• 特別な営業や宣伝をしなくても、
人に影響を与えられる
• 疲れを感じず、
結果や成功にこだわらない
• 存在そのものがエネルギーとなり、
人や社会に貢献する
これは、
自分の存在そのものが
仕事として機能する状態です。
自分の行動が
「良い」「悪い」といった評価を超えて、
ただ淡々と続けられる。
いつやめてもいいし、
いつまでも続けてもいい。
その自然な流れの中で、
人や社会に貢献できるという感覚です。

2. 天職を受け取るための鍵は、
状態=天職
人はつい、
「天職は外にあるもの」と考えがちです。
けれど、
実は天職は特定の
条件ではなく、
状態なのです。
天職 = 状態 ≠ 条件
「この仕事なら天職だ」
「この条件が揃えば天職だ」
という考えは、
実は自分が作り出した思い込みに過ぎません。
本当の天職は、
今この瞬間と深くつながり、
直感を信じて生きる中で
自然と現れてくるものです。

たとえば、
今している仕事が自分にとって
意味があると感じられるのは、
仕事そのものではなく、
自分の在り方によるものです。
逆に言えば、
どんな仕事でも、
その瞬間に今こことつながっていれば、
天職になり得るのです。
3. どうすれば現職が
天職になるのか?
では、
今の仕事が「天職」に感じられない場合、
どうすればいいのでしょうか?
1) 自分の思い込みや条件付けを知り、
解放する
まず、自分が今の仕事に対して
どんな条件付けをしているのかを
知ることが大切です。
• 「この仕事は安定しているから」
• 「評価されるから続けている」
• 「これしかできないから」
こうした理由はすべて、
自分の中にある思い込みや枠です。

これらを一つ一つ見つめ直し、
「本当にそれが必要なのか?」
と問いかけることで、
自分の心の中にある制限を外していけます。
2) 終わりや結果への執着を手放す
人は仕事に対して
「成功するか」「失敗するか」と
いった結果に縛られがちです。
しかし、
結果や終わりに対する恐れがある限り、
本当の意味で、
仕事に没頭することはできません。

「いつでもやめていいし、続けてもいい」
という自由な感覚で、
今に向き合うことが、
結果的に仕事への情熱を呼び起こし、
天職への道を開きます。
4. まとめ:天職はあなたの中にある
と言う事で、
天職は、特別なスキルや
環境の中にあるものではありません。
自分の在り方を見つめ直し、
今この瞬間と深くつながることで、
どんな仕事も天職に変わります。
もし今の仕事に迷いを感じているなら、
自分の中の
「こうでなければならない」
という条件付けを、
少しずつ解放してみましょう。
そして、
ただ今この瞬間に
意識を向けることから始めてみてください。
もしかしたら、
あなたの中に眠っている天職が
自然と顔を出してくるかも知れませんね。

この考え方は、
この存在が日々の仕事の中で実践し、
感じているものです。
またカウンセリングでは別料金ですが、
この様なワークを行ったりしています。
こんにちは。(^^)
本日は立春。
暦の上で春の始まりとされる日。
寒さがまだ残るとはいえ、
ここから徐々に春の気が満ちていきます。

昔の日本では、
立春を一年の始まりと考えていて、
旧暦ではこの日から新しい年が始まるとも言われていました。
豆まきをする節分も、
もともとは「立春の前日」であり、
「新しい季節に向けて、不要なものを祓う」
意味が込めていたみたいですね。

まあそれもさらに古代に遡ると、
意味は変わってきますが。
今日は、
痛みが教えてくれるもの
と言う視点のお話です。
整体の施術をしていると、
痛みを抱えて来院される方の多くが、
「痛みをなくしたい」
と言われます。
一般的には当然のことですね。
痛みは不快で、
日常生活に支障をきたすもの。
というのが常識だと思われてますから。
ですが、
「痛みを取り除く」ことよりも、
痛みが
何を伝えようとしているのか?
を、
感じ取ることも、
とても大事な視点になります。

実は痛みは、
単なる肉体の現象ではなく、
流れが滞った結果
として現れるものだからです。
それは、
筋肉や関節の滞りだけでなく、
自立神経の滞り、
心の滞り、
人生の流れの滞り
ともつながっています。
そう
「痛みを消す」だけでなく、
「流れを思い出す」を選択の一つに
持って頂きたいかな。

多くの人は、
痛みを「悪いものや、敵」だ
と考えます。
ですが、
痛みは自然物であり、
最大の味方である身体が、
全てのバランスを取り戻そうとする力の
表れでもあります。
例えば、
長年の肩こりがある人。
その人が抱えているのは、
単なる筋肉の問題ではなく、
「力を抜くことを忘れてしまった身体」です。
無意識のうちに緊張し、
肩を上げ、頑張り続けている。
「本当は、もう力を抜いてもいいのに」
身体はそう伝えたいのかもしれません。

整体を通して
身体の詰まりをほどいていくと、
ある瞬間、
フッと気づくことがあります。
「あれ? こんなに楽に息ができたんだ」
「こんなに腕が軽かったんだ」
それは、
ただ筋肉が緩んだだけではなく、
意識の奥にあった力みが解放された瞬間です。
痛みは「出口」でもある。
整体に来られる方の中には、
施術を受けている最中や後に、
「涙が出そうになった」
「なんだか心が軽くなった」
と言われる方もいます。
それは、
痛みが出口になった瞬間。

身体に滞ったものが、
感情や思考とともに流れ出す。
身体は、本来の動きを取り戻す。
意識もまた、それに呼応する。
痛みは、
「ここで何かが滞っている」
というサインであり、
そこに気づいたとき、
流れは自然と戻っていきます。
流れに乗るためにできること。
整体は、
単に「歪みを整える」もの
ではなく、
「流れを思い出す」ための
時間でもあります。

痛みを感じたとき、
まずはこう問いかけてみてください。
「これって何?」
「今、どこで力んでいるのだろう?」
「何を守ろうとして、この痛みを感じているのだろう?」
「もし、この痛みが教えてくれていることがあるとしたら?」
そうして身体の声に耳を傾けると、
痛みは「消すべきもの」ではなく、
「対話すべきもの」に変わります。
整体を受けることは、
ただ身体を整えることではなく、
意識の流れを取り戻すことでもあります。
痛みを通して、
あなたの身体が何を
伝えようとしているのか。
それを感じることで、
身体の流れも、
人生の流れも、
より軽やかになっていくかもしれません。
^ ^
さあ新年、
明けましておめでとうございます!

おだやかな朝を迎えられたでしょうか?
元旦は去年と同じく、
人の少ない天然温泉へ。
恒例の湯船に浮かぶ日本酒の香り。^ ^

そこから立ち昇る湯気が、
そっと空へと消えていく。。。
草木は風に揺れ、
湯気はゆっくりと流れ、
何ひとつ焦らず、
只々その時の流れに
身を任せているように見えます。
それは、
身体もきっと同じかなぁ。
朝からバスケの練習に付き合い、
普段使わない筋肉を痛めて、
肩や腰が少し重く感じるとき、
それは身体が「ちょっと休もうか」と、
教えてくれているのかもしれません。

無理をせず、
その声に耳を傾ける。
すると、
湯気がふわっと軽やかに昇るように、
身体も少し楽になっていく気がします。
自然のように、
身体を整える時間、
湯気や草木が、
何かを証明しようとすることはありません。
ただ「あるがまま」に
その瞬間を生きています。
身体もまた、
そうでありたいものです。
力を入れすぎず、
無理をせず、
自然な流れに身を任せる。

整体はその流れを整えるためのひととき。
湯気が風に揺れるように、
身体もその自然なリズムを取り戻すお手伝いができたらと思っています。
新しい年、
この一年が、
柔らかく、
穏やかな流れの中で始まり、
気づきで満ち、
湯気のようにふわっと軽く、
草木のようにしなやかに――。
そんな時間を重ねていけたら素敵ですね。
もし身体が
少し疲れを感じたときには、
その流れを整えるお手伝いができることを
願っています。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは。
気がつけば年末。

日の入りに礼。
そして
ふと立ち止まると、
よくある思考パターンとして、
気がつけば
「今年の自分」と「来年の自分」を
分けて考えたり、
「達成できたこと」と「まだ足りないこと」
を比べたりします。
でも、本当にそれらは
分かたれたものなのでしょうか?
実は比較こそが、
引き寄せたくない現実を、
作り上げているかも?
どうなんでしょうね。^ ^
そして来年は蛇年。
蛇はたくさんの象徴になり、
古代から多くの文化では
「境界を超える存在」
として描かれてきました。
例えば、
地上と地下、
水と陸を自由に行き来するその姿は、
私たちが作り出した
「分離」という錯覚を
問いかけてくれるようです。

蛇の動きは曲がりくねり、
一見するとどこに向かっているのかわからないように見えます。
でも、実は蛇にとって、
それそのものがひとつの道です。
曲がりや直線、
上りや下りという区別は、
人が後からつけたものにすぎません。
「良い」「悪い」と分ける経験もまた、
すべてがひとつの流れの中にあります。
今年の出来事を
「成功」と「失敗」に分けることなく、
ただそのまま受け入れるとき、
そこには何の不足もない
ひとときの道が、
見えてくるかも知れませんね。

この一年、
多くの方々に支えられ、
穏やかな時間の中で皆さまと向き合えたことに、
心から感謝しています。
新しい年が、
皆さまにとって、
蛇のようにしなやかで
柔軟な一年となりますように。
どうぞご自愛いただき、
心穏やかに新年をお迎えください。
来年も
進化してまいりましょう!
本年もありがとうございました。
こんにちは。
世間では子供や高齢者の間に、
インフルエンザが流行っているみたいですね。

誰でもかかるわけでなく、
身体に鉛などの有害ミネラルが多かったり、
ビタミンDが少なかったり、
血液循環が悪い方が
かかるものかなと
思いますが、
今日はそんなミネラルをお風呂で摂取する商品のお話です。

やっぱりお風呂が、
なんとも至福を感じさせてくれる、
日常の時間になりますね。
邪気まみれの方は、
お風呂に入るのを嫌がりますが、
やっぱりお風呂は良いです。
中でも日本は温泉地なので、
天然温泉はミネラルたっぷりが、
日常の疲れを癒してくれます。
ただ、
温泉場の弱点は、
たくさんの方が入るために、
塩素消毒も強くなってしまう事。

肌が弱い方には、
荒れる原因にもなりますね。
そんな入浴に、温泉の代わりに
お風呂に使ってもらいたいものがあります。
それは、
ufv入浴剤。
こちらは、
知り合いの先生から教えてもらった、
素晴らしい商品の一つ。
去年もひっそりと置いてましたが、
今回は独り占めせずに、
お知らせしました。
内容の説明としては、
ミネラルたっぷりの天然素材に、
生命の代謝や育成に欠かせない
と言われているテラヘルツ波の中でも、
さらなる超微振動を発生させる
ufv (ウルトラファインバイブレーション)。
をおこすという、
独自の技術で加工された入浴剤です。

入浴時に振動はまったく感じませんが、
体内では超微振動の還元作用による
抗酸化作用がもたらされ、
代謝を上げると、
同時に毛穴に溜まった汚れや、
古くなった角質を取り除いて、
肌がものすごいツルツルになります。
浴槽もツルツルに掃除も楽々。笑
見えないものもツルツルに払い流します。
加えて、冬場にこもりやすい、
ニオイのケアもしてくれます。

効果は全身だけでなく、
それを頭皮や毛髪に使ったり。
肌荒れの原因となる
残留塩素も除去してくれるので、
もしも敏感肌の方や、
赤ちゃんでも入浴が可能です。
箕面の温泉のような
トロトロのお湯と、
シュワシュワな微細な泡で、
じわじわ発汗し、
代謝を改善し、
全身のポカポカが実感できます。^ ^

原料として、
ミネラル塩、
ココヤシ果実、
アロエベラ葉エキス、
レモン果実エキス、
カニナバラ果実エキス、
ソケイ花エキス、
ホホバ種子油、
月見草油、
ブドウ種子油、
キョウニン油、
マツ種子油
が使われています。
温泉に行けない日にはオススメです。^ ^

他にも、
エプソムソルトも、
皮膚からマグネシウムをたくさん吸収できるので、今回のufv入浴剤とセットで使うと、
かなり至高のお湯になりますね。^ ^
みなさんこんにちは!
今日は21日、
いよいよ冬至ですね。
冬至って言うたら、
厄落としに
「かぼちゃ」「ゆず湯」が定番…か、
と思いきや今日はちょっと変わった
アイデアをご提案!

それが、恒例のお礼参りです、
お礼参りってどんなこと??
お礼参りとは、
その年お世話になった場所や人に
「ありがとう」を伝える行動のこと
ですね。
もちろん家族にもね。
冬至は、陰が一番強く、
「これから光が戻ってくる」
即ち新しいエネルギーが始まる日。
だから、
冬至にお礼参りをしておくと、
気持ちもスッキリして、
次の一年のスタートが、
より良いものになれるかも、
という話です。
冬至の七草も、運を取り入れるかも?

そんな冬至におすすめのお礼参り
3ステップ!
1. 神社で感謝を伝える
冬至の日に神社に行って、
「今年一年、無事に過ごせたことをありがとうございます」と感謝を伝えるのが、お礼参りの第一歩です。
• ポイントは、
お礼参りのときは、
「感謝」を伝えるだけでOKです。
お願い事は年末年始に回して、
「ありがとう」だけを
シンプルに伝えるのがコツです。
ついでに歩いて行くとさらに健康的ですね。
冬の冷たい空気の中を歩くと血流も良くなります。
整体的に見ても、
ウォーキングは腰痛や、
肩こり予防にも効果的です。

2. 家の掃除で環境に感謝
冬至の大掃除は、
お世話になった家や空間へのお礼の意味も込めてやると、さらに気分が上がります。
ポイントは、
玄関掃除が運気アップの鍵
「玄関は家の顔」
って言われるぐらい大事な場所です。
玄関を拭き掃除することで、
(掃き掃除より拭き掃除で。)
良い気を迎え入れる準備が整います!
• 掃除中も体をいたわる
雑巾がけで腰を痛めたり、
窓拭きで肩が張ったりする前に、
軽くストレッチをしておきましょう。
それでも疲れたら整体院でメンテナンスの予約を。

3. 体に感謝
最後に体にも
「今年一年、よく頑張ってくれたね」と、
お礼を伝えるつもりで、
整体やしっかりした運動で、
体をリセット。
冬至は夜更かしはやめて、
早寝、早起きでし!^ ^
更にポイントは、
血流を良くして循環促進。
冬はどうしても体が冷えやすくなります。
温泉やお風呂で入浴し、
(オススメはufv入浴剤。細胞が喜びます。)
筋肉をほぐすために、
軽めの筋トレ。
もしくは血行を促進して、
首を温めましょう。
急所は足首、手首、腰首、首。
でポカポカの体へ!
来年に向けた体つくりを始める!
年末は忙しくて体が固まりがちですから、
冬至から意識して身体を循環し整えておくと、
次の一年をスムーズにスタートできるかも!

まあ、簡単にまとめると、
• 「毎日使ってる玄関やリビングを拭き掃除しながら、ありがとうと言う」
• 「神社で空気を吸いながら、目に映る自然に感謝する」
• 「体を触りながら、ありがとうって言って早く寝てみる」
みたいな。
気分がスッキリして、
なんだか心が軽くなるはずです。
冬至は、
「一年の雛形」になると言われる大事な日。
拭き掃除で家を整え、
神社参りで感謝を伝え、
整体や運動で体を循環すれば、
とても理想的ですが。
お仕事や用事で難しい方は、
最低限、
今日だけは、
とりあえず愚痴や悪態をやめてみましょう。
後は循環の為に、
少しだけ外を歩きましょう!
来年の雛形なんでね。^ ^
気持ちも体も、
新年スムーズに過ごせるかもです。

みなさんこんにちは。
12月はどんな日々をお過ごしでしょうか?

先日、頭蓋に低周波を当てて、
全身の痛みを消してしまう?
と、いう体験会に誘われて、参加してきました。
もともとですけど、
痛みを消すとか、
痛みを治すとか、
そういう言葉には、
自然の摂理から見ると、
自己中というか。
強制的過ぎて、
さっぱり魅力を感じなかったのですが、
お誘いの方が是非にと言われていたので、
行ってみると、
思った以上にたくさんの主婦層や、
ご高齢の層が来られてました。
説明を聞いて、
施術を見させていただいた結果、
詳しくは言えませんが、
静かに退場させて頂きました。
ワクちゃんの件には反対をされているような
方達の参加だったんですが、

権威のある方が作っていようとも、
強力なパワーの機械を扱う時には、
多少は勉強が必要かもねと感じました。
そんな感じで、
今日は頭蓋骨調整の魅力について。
みなさんは、
「頭を整えることで全身が楽になる」
という話を聞いたことがありますか?
何度かブログでも紹介していますが、
かなり前ですね。
実は、
頭の中にあるリズムや圧力は、
驚くほど全身に
大きな影響を与えています。

整体の世界では、
クラニアル(頭蓋骨調整)という手法で、
頭蓋骨や脳脊髄液、
神経の働きを優しく整えることで、
体の不調を解消するアプローチがあります。
今日はそのクラニアルについて、
分かりやすくお話ししていきます。
クラニアル(頭蓋骨調整)とは、
頭蓋骨のわずかな動きや、
リズムを感じ取り、
一次呼吸と呼ばれる波に、
サーフィンのように逆らわずに整える施術です。

「え?頭蓋骨って動くの?」
と驚く方もいるかもしれませんが、
実際には頭蓋骨は微細な動きをしています。
この動きが乱れると、
全身に影響が及ぶことがあります。
例えば、
脳脊髄液の流れが滞る。
栄養障害や、睡眠障害につながったり、
神経伝達がスムーズにいかなくなる。
発達障害や、認知障害などにつながったり、
血流やリンパの循環が悪くなる。
頭痛や、難聴、緑内障などの障害につながったり。
クラニアルでは、
こうした問題に対して、身体が持つ、
自然治癒力を引き出すことを目指します。

クラニアルで、
どんな効果が期待できるのか?
クラニアルは特に以下のような症状や悩みに効果が期待されています。
1. 頭痛や首のこり
頭の緊張が解放されることで、
頭痛や首のこりが軽くなることがあります。
2. 自律神経の調整
頭蓋骨を整えることで、
副交感神経が優位になり、
リラックス効果が得られます。

3. 全身の疲れや不調
頭と体のリズムが整うことで、
血中コルチゾール値が下がり
全身の疲れやだるさが軽減されることがあります。
4. 睡眠の質向上
頭の緊張が取れると、短くても
深い眠りにつながることもあります。
クラニアルの施術はとてもやさしく、
10g以下の力で行います。
力任せに頭を押したりすることはなく、
施術者の手を頭にそっと置き、
頭蓋骨や脳脊髄液のリズムを感じ取りながら進めます。
この施術中、
クライアントの多くは
「深いリラックス」を感じたり、
「身体がふわっと軽くなる感覚」
を体験します。

クラニアルは特に以下のような方におすすめです。
• 慢性的な頭痛や首の不調がある
• ストレスが多くて身体が緊張している
• 睡眠が浅い、よく眠れない
• 全身の疲れが抜けない
• リラックスしたいけど、どうしても力が抜けない
みたいな。
身体の痛みを改善するためには、
どうしても「早く治したい」と
焦ってしまいがちです。
でも実は、
体が持つ自然な癒しの力を
引き出すためには、
「無理に治そうとしない」
ということがとても大切なんですね。
(スペースの無い人ほどわかってなかったりしますが。)
どうしてこんなに痛いの!!?
と体に問い詰めるのではなくて、
痛みを使って何が体を整えたがっているの??
と、
やさしく耳を傾けてみるんです。
体は、
治りたい力を持っています。
しゃべれませんからわかりにくいかもですが。
クラニアルは、
「身体は自分で整える力を持っている」
ということを思い出させてくれる施術です。

頭をそっと手を整えるだけで、
全身が軽くなり、
自然と不調が改善される感覚を。
興味がある方はぜひ体験してみてください。
^ ^
当院では、
この存在が治すのではなく、
治してもらうのでもない。
身体が持っている自然治癒力を、
スペースと意識と一緒に
最大限に引き出すお手伝いをさせて頂いています!

















